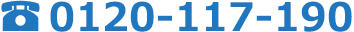いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
今日は『リサイクルの日』です。今までは捨てるしかなかった
物を買い取ってもらえるお店が最近は増えていますね。
是非、この機会に持ち込んでみてはいかがでしょうか。
さて、前回までの5回に渡り食品共同配送の成功する例を
お伝えさせていただきました。
その都度注意点を書き添えさせていただきましたが、今回は
それらを含め改めて注意点をお話ししたいと思います。
1 納品時間は帯で考える
共同配送は言わば乗合バスと一緒。
様々な製品を日々変動する物量に対応しながらいろいろな
ところに配送しますから、納品時間をピンポイントに何時と
指定しての配送は難しいと考えましょう。
例えば8:00~12:00のようにできるだけ広い帯で納品
許可を取ってください。
2 同じ製品でも配送距離や納品条件などで単価は変わる
共同配送はケース単価や訪問件数単価などの運賃設定が多い
のですが、基本になるのは時間と距離が多いようです。
遠方になれば高くなりますし、陳列など時間が掛かる納品方法
を依頼すれば当然通常より高い単価になります。
また、基準より重い・大きい場合も割増の可能性があります。
参考までに当社の基準は、1才7Kgになっています。
3 匂いに注意
乳製品など移り香に弱い製品は要注意です。
安価な配送料だからと共同配送にした結果、他の食品の匂い
が移ってしまい全量返品というケースも稀にあるようです。
混載される可能性のある製品の確認や、場合によっては
共同配送をあきらめることも必要です。
4 主導権は物流会社
チャーター配送はそのお客様の専属ですから、ルートや時間など
のアレンジはお客様の自由ですが、共同配送では他の製品を
混載する性格上、主導権は物流会社になります。
各物流会社のルールや規則に合わせる必要がありますので、
事前に確認をしておく必要があります。
5 必ずしも安くなるわけではない
共同配送はケース単価や件数単価の為、物量に応じた
配送費にできるメリットがある手段ですが、物量が増えてくる
と返って高くついてしまうこともあり得ます。
適正な配送費を考えるなら、共同配送に偏らずチャーター配送や
路線便など他の手段も検討する必要があります。
これら以外にも注意点はありますが、結局のところ最も大切な
ことは、物流会社と信頼関係を築けるように情報交換を密にする
ことではないかと思います。
食品の共同配送をお探しの方は こちら から。
食品の業種別配送ソリューションは こちら から。