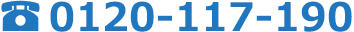先日のヤマト運輸クール宅急便常温仕分けの報道を聞いて、
おそらく冷凍・チルドの物流企業においてはさほど驚きは
なかったのではないかと感じています。
それは、起こる可能性が事前に十分に予測できたからです。
あくまで私の予測ですが、この問題の原因は急速に宅配や
通信販売の業界が成長してきたことに対して、人財教育を
はじめとする環境整備が追い付いていないことだと考えられ
ます。
もともとクール便はお中元やお歳暮を中心に、遠隔地からの
食材などを一時的に配送するときに有効な手段として、
消費者に認識されてきた利便性の高いサービスです。
ですから、冷蔵・冷凍の仕分けは通常ならば安全性を考えて
冷蔵冷凍倉庫で行われるのが常ではありますが、当初扱い
個数の少なかったクール便は、一般の宅急便が仕分け
される施設の片隅でコンテナの開け閉めの対応を考える
程度で十分だったと考えられます。
それがここ数年、日常消費するものまで通販などで購入する
消費者が爆発的に増えてきた関係で、ヤマト運輸の宅急便
という、利便性も信頼性も高いサービスに需要が集中して
しまいました。
このような情勢を考えれば、当然施設やその対応方法を
変えていかなければいけなかったと思います。
また、温度管理を必要とする製品を取り扱うためには、
最低限守らなければいけないことや温度変化の特性について
の知識が必要で、それらを習得するにはある程度の時間と
経験が必要になります。
もちろんヤマト運輸もこの業態を成長戦略と考えて、設備の
増強や人材の育成、オペレーションの強化などに注力して
きたと思いますが、あまりにもそのスピードが速過ぎて
追いつかなかったのではないかと思うのです。
今回の問題は、中小の物流会社でしたらさほど問題に
ならなかったかもしれません。
ヤマト運輸の宅急便という信頼性の高いブランドだからこそ
これだけの報道がされたのだと思います。
ですが、これを対岸の火事と考えず、自社の中に同じような
トラブルの種が存在していないか検証する機会にしたいと
思います。
食品のチャーター輸送をお考えなら こちら から。
食品の共同配送をお探しの方は こちら から。