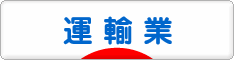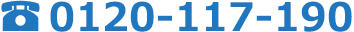茨城県・栃木県の冷凍・冷蔵食品物流なら茨城乳配にご相談を!!
ブログ更新2631回目。
船井総研ロジ社主催の物流研究会LPS10月度例会に
参加しました。
すっかりZoomでの開催が定着して、リアル開催に
なっても行く気になるのか不安です…
今回の収穫は3つ。
物流企業同士の情報交換会の時間の中からは、
指差呼称の徹底に関する情報と、コロナ感染時の競合との
協力体制の構築についての情報でした。
品質向上を図るために、以前から物流現場で取り組まれて
いるのが指差呼称。
チェック項目を指で指し示し「ヨシ!」と発声して
確認するものです。
これを徹底するとヒューマンエラーがみるみる減少すると
言われていますが、その徹底が本当に難しく挫折する
企業は少なくありません。
茨城乳配でも取り組んでみたことがありますが、浸透せずに
グダグダになってしまった苦い経験があります。
今回、ある企業から浸透プロセスを計画してスタートさせた
という発表がありました。
内容が参考になるものだったので次期経営計画に盛り込んで
再チャレンジしてみようと思います。
もう1つの、コロナ感染時に競合他社がお互い協力し合う
取り組みも興味深いものでした。
もし自社内でコロナ感染者が発生した場合、自ら業務の
穴埋めすることは事実上不可能です。
そういった状況に陥った際に、同じお客様の仕事をする、
日頃は競争関係にある企業同士が協力し合うことで
お客様へのサービスを破綻させないように契約を結んだ
という事例発表でした。
消費者にとって、荷主企業にとって、物流事業者にとって。
それぞれメリットの大きい取り組みです。
もしこういった協力体制が取れずに窮地に陥れば大手企業の
参入を許すことにもつながるので、我々も準備すべき施策だと
感じました。
ただし、これはどこの企業と組むのか判断が難しい部分が
あります。
慎重に検討していきたい施策です。
3つ目の気づきは、最終講座から。
将来の管理職の育成に関することだったのですが、
自分の子供をどんな学校に入れたいかを考えれば
管理職が育つ会社の”あるべき姿”は見えてくるという
お話でした。
カリキュラムと評価指標と、サポート体制が整っていて、
計画性があること。
大手企業ならば当たり前にあるものですが、中小企業は
これらの整備が遅れがちです。
将来必要なマネージャーの育成とデジタル化は、今後の
3か年計画にも盛り込む予定でしたので、どのように
施策を構築していくかのヒントを得ることができました。
この3つの気づきについて、次回の経営会議で話し合って
みようと思います。
↓ランキングに参加中です。クリックのご協力をお願いします!!