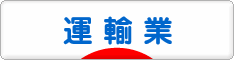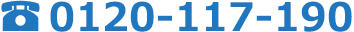茨城県・栃木県の冷凍・冷蔵食品物流なら茨城乳配にご相談を!!
ブログ更新2692回目。
私が考える食品共同配送におけるデジタル化への課題を
お話するシリーズ第4弾です。
今日は、設備投資についてお話しします。
デジタル化の大きな課題と言えば、”おカネ”が挙げられます。
労働集約型の輸配送業界は、さほど大きくないイニシャルコストで
事業を始められるのでこれまで多数の企業が参入してきました。
したがい、価格競争が激しくなり収益率の低い業界になって
います。
デジタル化された未来の姿を俯瞰してみると、これまでなかった
設備への先行投資が必要であることが浮き彫りになってきます。
例えば、オートメーションな倉庫を持とうとすればイニシャルで
大きな投資が必要になります。
仮に賃貸で調達するとしてもそれ相応の賃貸料を払うことになるので
それが支払える受注力や企業の体力が必要になります。
また、トラックに装備するデジタル化システムにも大きな投資が
必要になります。
デジタルタコグラフやドライブレコーダーはもちろんのこと、
動態管理やオートルートシステム、車両データをリアルタイムで
送受信するためのシステムも必要になるでしょう。
共同配送であれば、不特定多数の荷主企業の貨物量を短時間で
集計し最適なトラック台数と配送コ―スをはじき出すシステムが
必須になります。
そう考えると、低い収益率の業界でそれだけの投資ができるのかという
問題が出てきます。
食品は人が生きるために必要なもの。
毎日消費されるものであることからも商品に大きな価格転嫁はできません。
従って物流費を大幅に引き上げることも難しくなります。
無理にデジタル化を急ぐ必要はありませんが、荷主企業が確実に
デジタル化を進めていることを考えると、そこと繋がることが
できる環境整備としてのデジタル化は必須になります。
労働集約型から資本集約型に移行することになると、
中小企業の体力でできることは限られるので、
今のうちに中堅企業クラス以上への成長を遂げて、
資本力を養うことが求められていくのでしょうね。
↓ランキングに参加中です。クリックのご協力をお願いします!!