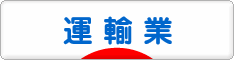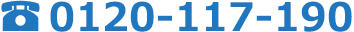茨城県・栃木県の冷凍・冷蔵食品物流なら茨城乳配にご相談を!!
ブログ更新2753回目。
政府が今月2日に10都府県で緊急事態宣言を1ヵ月延長したのを受け、
外食企業と取引する物流事業者は重要な意思決定に迫られています。
宣言が再発令されて以降、飲食店への時短営業要請のあおりで
業務用卸や酒類・食材メーカーなどの売上げが激減。
当然、物量が減ったことで物流センターは想定通過量を下回り、
輸配送トラックの積載効率は一気に悪化しました。
もちろん需要に合わせた調整は行われていて、ドラッグストアや
食品スーパーの特需対応へのスポット参戦や、人手不足時に
溜まった公休・有休の取得、社員への教育研修などを積極的に行う
物流企業もあるようですが、しかしこれは状況が落ち着くまでの
一時的な措置でしかありません。
外食企業の多くは店舗の閉鎖や統廃合を加速させており、仮に
コロナウイルスの流行が沈静化して外食利用者が戻ってきたとしても
物量はコロナ前の水準から大きく下落することが明らか。
その減少分を何らかの新規業務で埋めるか、単純にスケールダウンを
甘んじるかという選択に迫られています。
売上好調な小売企業の物流が活性化していることから、そちらへの
シフトを考えたいところだが、外食物流と小売り物流ではノウハウが
違いますし、ドライバー職の希望就労時間帯にもギャップが
生まれてしまいます。
加えて、小売りの物流を担う既存競合のガードも高くなりますから
それほど簡単にシフトできる話ではないというのが現状です。
そして何より、今までお世話になってきた既存外食顧客との関係を
考えると、さらに難しい判断を迫られます。
とは言え、外食企業に食材を納入している食品卸売り企業は公的支援を
受けられていないことから、販管費のさらなる削減や合理化を模索するので、
物流コストにも当然目が向けられてくるでしょう。
大手企業による、より多くの外食企業の物流を共同化する動きも出てくる
ことが予想されます。
そうなれば全体のパイはさらに絞られることに。
中小物流企業は外食物流部門の未来をどのように描くかが問われることに
なりそうです。
↓ランキングに参加中です。クリックのご協力をお願いします!!