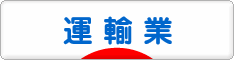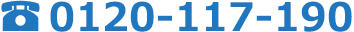茨城県・栃木県の冷凍・冷蔵食品物流なら茨城乳配にご相談を!!
ブログ更新2299回目。
少し前にUSJの森岡氏のよってビジネス領域で注目された定量分析。
その後には様々な書籍も販売され、世間では”ハカる”ブームが
起きました。
でも、プロのようにはなかなか分析できませんね。
当社でもいろいろな分析にチャレンジしていますが、
ファクトとして自信をもって使える分析結果はなかなか
導き出せていません。
茨城乳配が得意とする冷凍・冷蔵食品の共同配送サービス。
ホームページには自信ありげに「お任せください」なんて
書いてありますが、
「こいつら、本当に共同配送の実力あるのか?」
と疑問に思うことがあるでしょう。
共同配送というシステムの能力を”ハカろう”とする場合、
どのように考えたら良いのか迷いますね。
共同配送をハカる方法。
ズバリ! 食品の共同配送を検討するには、以下の3つを見れば
ハカれます。
・エリアのカバー率 (全国?都道府県?市町村?)
・エリア内の密度 (エリア内車両数は何台?)
・スタッフの定着率(スタッフの対応力は?)
エリアの広さ×密度の深さ×人材能力が重要になります。
「え、価格が一番でしょ?」
そういう声が聞こえてきそうですが、それは最後にお話します。
エリアのカバー率については、特定の市内に強いのか、どこかの
特定の都道府県内に強いのか、全国規模に対応できるのかという
視点になります。
通常は全国に対応できる企業が良いよね、的な発想になりがちなんですが、
そう言えない理由が次の密度になるんです。
エリアでの強さは密度で決まります。
どれくらいエリア内を網羅しているかをハカる指標です。
例えば、茨城県内に強いというA社とB社の輸配送会社があるとします。
両社ともに茨城県内全域をカバーしています。
でも、A社は県内を10台のトラックで共同配送サービスを提供しており、
B社は20台のトラックで共同配送サービスを提供しているとすると
どうでしょうか。
A社は1台のトラックが長い距離と時間をかけてカバー―することに
なるので、時間指定やイレギュラー、またトラブル対応が遅くなります。
一方で、B社は倍のトラックで運行しているので物量の増減や時間指定
などにフレキシブルに対応が可能になります。
今話題の働き方改革は物流業界にも大きな影響があるので、
コンプライアンスの観点からも後者のほうがリスクが低くなります。
「じゃ、無理して台数を動かせば同じ能力だよね?」
その通りです。
でも、冷凍・冷蔵食品物流というのは止まらない物流というのが
最大の特徴なんです。
毎日動くことは利点ですが、一方で薄利という特徴もあります。
日常消耗品である食品は、消費者の単価変動への反応が敏感で
価格転嫁が難しいからです。
ゆえに、毎日赤字を出しながら継続できるものではないんです。
つまり、広いエリアを密度を高めてサービス提供できる企業は、
それなりの荷主企業から信頼されて物量を任されている企業であり、
だから採算面でも心配なく実現できていると言えるわけです。
エリアに対する密度が高いことはそれだけで大きな強みに
なるわけですが、これは固定費にあたるバックオフィスコストや
センター運営費を抑制できる強みにもなります。
総務部門や運行管理部門、またそれぞれのシステムのコストは
固定費となり物量が多いほうが希釈化します。
一方で、物流業界は労働集約型の業界ですから、最もおカネが
かかるのは人件費です。
人手不足の環境下では、離職率が高く現状の業務を維持することが
困難な企業が多くなっています。
こうなると、常に採用コストと教育コストが積み増されますし、
経験の浅い社員の割合が高まることでフレキシブルな対応や安全面に
不安を抱えるようになっていきます。
逆に言えば、スタッフの定着率が高い企業は、各教育が浸透しやすく、
実務で得られる暗黙知や経験則からの判断力に厚みが生まれるので、
採用・教育コスト以外にも臨機応変な対応が自然と出来ることにより、
おカネでは解決できないピンチを切り抜けられる可能性が高まるんです。
定着率=能力=コスパ
あれ、いつの間にかおカネの話になってしまいました。
そうそう、これが価格のお話です。
エリアの密度が高くて定着率が高い企業ほど、ケース当りの単価や
イレギュラー対応、物量の変動などを考慮した場合のトータルコストは
安くということです。
まとめ。
全国規模に対応できるといっても密度が粗ければ意味がありません。
エリアに対する密度が重要。
そして、なによりスタッフが業務に精通しているか、また初心者を
早期に戦力化できるかといった能力開発ができるかが重要です。
それがコストに跳ね返るし、コンプライアンスにも影響します。
だから共同配送の委託先を検討する場合は、これらの指標を
しっかりハカって選んでくださいね。
最後に大手企業の役割という疑問について。
大手企業ならなんでもできるんじゃないか、っていう疑問。
大手企業の強みは、一括でそれらをまとめて全体最適な仕組みを
提案できる点と、初期投資が莫大になる場合に資金力がある点です。
一方で、組織が大きいため固定費が固く、目標収益率も中小企業に
対して莫大な設定になっています。
要するに、輸配送費が高い。
実際は、大手企業がエリア企業に提案作成のアドバイスを依頼
したり、エリア企業に骨子を作ってもらってそれに自社の取り分を
上乗せして荷主企業に請求しているなんて話は少なくありません。
食品の輸配送のような小さなコスト改善の積み重ねが必須の
業務では、選択に十分注意が必要だと思います。
自社の物流をどの規模の物流企業に相談したらわからない場合は、
茨城乳配に相談してみてください。
当社では、物流診断させていただき、その結果によって最適な
物流をご提案させていただいています。
最適と判断されれば、他の物流企業をご紹介することもあります。
↓ランキングに参加中です。クリックのご協力をお願いします!!