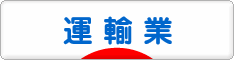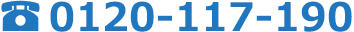茨城県・栃木県の冷凍・冷蔵食品物流なら茨城乳配にご相談を!!
ブログ更新2912回目。

冷凍輸配送と冷蔵(チルド)輸配送では注意点に違いがあるの?
このような質問を頂くことがあります。
今日は、基本的な違いについてお話してみようと思います。
まず大きな違いは温度帯です。
このブログでも何度か取り上げていますが、食品物流には
商品カテゴリーによって複数の温度帯が存在します。
物流各社によって様々な解釈やこだわりがあるようですが、
概ね冷凍ならば-10℃以下の温度で管理されるものを冷凍輸送、
+5℃から-5℃の範囲で管理されているものを冷蔵(チルド)
輸送と考えれば良いでしょう。
冷蔵(チルド)輸送は温度が上がリ過ぎても下がり過ぎても
いけないという点が難しいところです。
例えば、実際の冷蔵(チルド)輸送の現場では、輸配送時の
納品訪問数によって荷台ドアの開閉回数が決まってきますので、
訪問数が多ければ開閉時間が増えて、商品を積載している荷室が
温度変化を起こす回数も増えるということになります。
冷蔵(チルド)食品はデリケートな商品が多いために、温度の
上昇は食品の発酵が進んだり、味が変化してしまうなど
商品にダメージを与える可能性が高くなります。
また温度上昇を恐れて温度設定を下げ過ぎてしまうと、凍結に
よって商品価値を失うことになることもあるので、常に温度を
把握し対応することが必要になります。
最近は、冷凍商品と冷蔵(チルド)商品を同時に運ぶことが可能な
2層式(2室型)の車両を使用するケースが増えてきましたが、
利便性が高い一方で床と隔壁から冷気が伝わって冷蔵(チルド)食品を
凍結させてしまう事故が多発しています。
このような車両を使用する場合には、隔壁から冷蔵(チルド)食品を
離して積載するなど工夫が必要になります。
一方冷凍輸送は、温度を絶対に上げてはいけない点が管理の難しさと
言えるでしょう。
そのために、準備する車両の仕様もそれに合ったものになるため、
冷蔵(チルド)輸送に比べて車両の調達コストが高額になります。
また、冷凍装置への負担が大きくなるので故障への対策が重要になります。
冷凍機の故障は溶解に繋がるため、車両の整備にも細心の注意が
必要になります。
整備コストの高額化を押さえるための日常点検と予防整備が重要になります。
いかがでしたでしょうか。
冷凍輸配送と冷蔵輸配送は似ているようでポイントが大きく違います。
物流企業を選定する際は、こういった温度管理のノウハウがあるかどうかを
確認して委託することをおすすめします。
===================
食品物流のエキスパート!冷蔵・冷凍輸送なら茨城乳配まで
◉関東エリアはおまかせ!茨城・栃木宇都宮・千葉・神奈川
◉冷蔵倉庫・冷凍倉庫を保有!保管まで対応
◉小口輸送・スポット便も柔軟に承ります
▷食品の共同配送サービスはこちら
▷冷蔵・冷凍輸送の運送会社・物流会社をお探しならこちら
▷輸送効率・運賃の見直しについて無料相談はこちら
まずはお問い合わせください♪
TEL:0120-117-190
問い合わせフォーム:https://nyuhai.net/contact/
↓ランキングに参加中です。クリックのご協力をお願いします!!